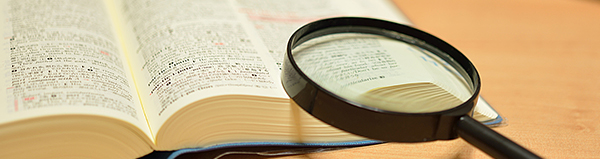公開日 2025年10月30日
令和7年度日本鱗翅学会において、石井理事長が、チョウ類の生活史と保全に関する研究に取組んできた業績により、日本鱗翅学会賞を受賞しました!
受賞概要
【受賞者】
理事長 石井 実(いしい みのる)
【業績名】
チョウ類の生活史と保全に関する研究
【業績概要】
長年にわたり里地里山に生息するチョウ類を中心とする昆虫類の生活史の解明に関する研究を進めるとともに、絶滅危惧チョウ類の保全に関する研究やチョウ類群集を指標とする里地里山の生物多様性保全に関する研究にも取組んできました。

図 ギフチョウの季節生活環と蛹休眠
どのような研究内容が評価されたの?
-
アゲハチョウ類の休眠性の地理的変異について研究を進め、ナガサキアゲハでは休眠を誘起する臨界日長や休眠蛹の耐寒性などの形質状態から、近年の急速な分布拡大は冬季の温暖化が要因であることを解明しました。
-
1年1世代の1化性昆虫の季節生活環について研究し、絶滅危惧種のギフチョウでは夏秋冬を越す長い蛹のステージが夏休眠と冬休眠という異なる性質の休眠を連続することで制御されていることを明らかにしました。(上図参照)
-
稲作害虫のイチモンジセセリの秋口の移動について調査研究を行い、移動成虫が大型の「短日型」に対応し、越冬幼虫の生存率が寒冷地では低いことなどから、温暖な地域での越冬が移動の生態学的意義のひとつであることを示しました。
-
大阪府北部の里山林「三草山ゼフィルスの森」においてチョウ類のモニタリング調査を継続し、植生管理について提言するとともに、群集解析のために寄主植物の出現する植生の遷移段階に基づく「SR指数」を考案しました。
研究成果はどのように活用できる?
- 南方系害虫の分布拡大地域の予測、1化性希少昆虫の生息域外保全技術の開発、移動性害虫の調査・研究方法の検討、里山林の植生の順応的管理などに活用できます。
受賞者のコメント
- 私のライフワークであるチョウ類の生活史と保全に関する研究で栄えある賞をいただけたことは喜びに堪えません。今回の受賞は多くの方々との共同研究として、あるいは多くの方々のご協力やご指導をいただきながら積み上げてきた研究成果が評価されたものであり、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

石井理事長
研究内容の詳細は環農水研までお問合せください。
「日本鱗翅学会賞」とは
日本鱗翅学会は、チョウやガを研究対象とする学術団体で、アマチュアから専門家まで幅広い層のメンバーが協力しながら活動しています。
日本鱗翅学会には学会賞、奨励賞があります。学会賞は、研究成果の発表・出版等、鱗翅学の発展普及に資する業績、鱗翅類やそれにかかわる事柄に関する社会的関心の増進のための活動、会務に関する貢献等に優れた功績をあげた者に授与されます。なお、受賞は毎年原則1名です。
日本鱗翅学会ホームページより抜粋
添付資料
■お問い合わせはこちら
企画部企画グループ
担当:森川、井戸川
[TEL]072-979-7070
[FAX]072-956-9691