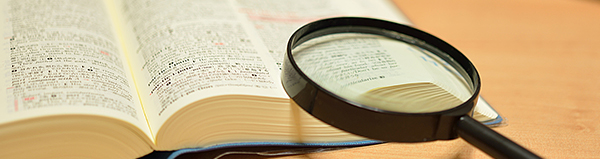生物多様性基本法について
生物多様性保全に関わる国の動き
生物多様性基本法
人類は生物多様性のもたらす恩恵を受けて生存しており、また、生物多様性は地域固有の財産として文化の多様性の基盤となっています。さらに我が国は工業資源や食料などを世界中から輸入するなど、経済活動の多くを世界の生物多様性に大きく依存しています。しかし、現在世界中で開発等による生物種の絶滅や生態系の破壊、外来種等による生態系のかく乱が起こり、さらには地球温暖化等の気候変動によって生物多様性の深刻な危機に直面しているとの認識から、「生物多様性基本法」が、平成20年6月6日に公布されました。
この法律の目的は”生物多様性の保全及び持続可能な利用”であり、その基本的施策としては、保全に重点を置いた施策(1. 地域の生物多様性の保全、2. 野生生物の種の多様性の保全等、3. 外来生物等による被害の防止など)と持続可能な利用に重点を置いた施策(4. 国土及び自然資源の適切な利用等の推進、5. 遺伝子など生物資源の適正な利用の推進、6. 生物多様性に配慮した事業活動の促進など)に分けられ、さらにこれらに共通の施策として、7. 地球温暖化の防止等に資する施策の推進、8. 多様な主体の連携・協働、民意の反映及び自発的な活動の促進、9. 基礎的な調査等の推進、10. 試験研究の充実など科学技術の振興、11. 教育、人材育成など国民の理解の増進、12. 事業計画の立案段階等での環境影響評価の推進、13. 国際的な連携の確保及び国際協力の推進があげられています。また、これらの施策の実施にあたって、国に「生物多様性国家戦略」策定の義務と地方公共団体については単独又は共同で策定する地方版戦略を努力義務として課しています。