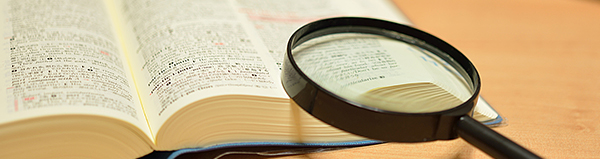生物多様性条約について
生物多様性保全に関わる国の動き
生物多様性条約
生物多様性は食糧、医療、科学等の基盤として、人類の生存を支え、人類に様々な恵みをもたらしています。しかし、近年、野生生物の種の絶滅がかつてない早さで進んでおり、その原因となっている自然環境の悪化や生態系の破壊に対する懸念が深刻なものとなっています。そこで、早急に生物多様性の喪失を食い止める手立てを講じる必要が生じています。
野生生物は人間の決めた国境にしばられずに生息しているため、個々の国でバラバラに生物多様性を保存しても有効な対策がとれず、世界全体で問題に取り組むことが重要です。このような事情を背景に、希少な生物の取引規制や特定の地域の生物種の保護を目的とする既存の国際条約(ワシントン条約、ラムサール条約等)を補い、生物の多様性を包括的に保全し、生物資源を持続に利用していくため、国際的な枠組みをつくることが国連等において議論されるようになりました。
その結果、1992年5月に,1. 生物多様性の保全、2. 生物多様性の構成要素の持続可能な利用、3. 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的として、「生物多様性条約」がつくられました。2010年9月現在、日本を含む193ヶ国がこの条約に入り、世界の生物多様性を保全するための具体的な取組が検討されています。また、1~2年間隔で生物多様性締約国会議が開催され、様々な議題について話し合われて決議が出されています。
この条約には、先進国の資金援助により開発途上国の取組を行う仕組みと、先進国の技術を開発途上国に提供する仕組みがあり、経済的・技術的な理由から生物多様性の保全と持続可能な利用のための取組が十分でない開発途上国に対する支援が行われることになっています。また、生物多様性に関する情報交換や調査研究を各国が協力して行うとともに、、”締約国はその個々の状況及び能力に応じ、生物多様性保全及び持続可能な利用のため「生物多様性国家戦略」を策定する”とされています。